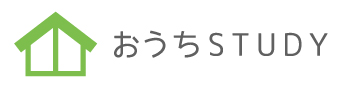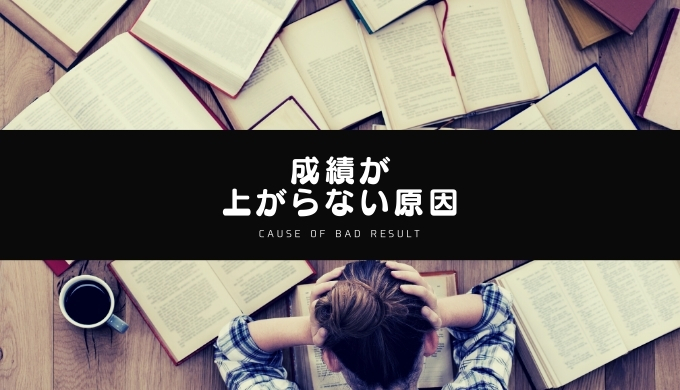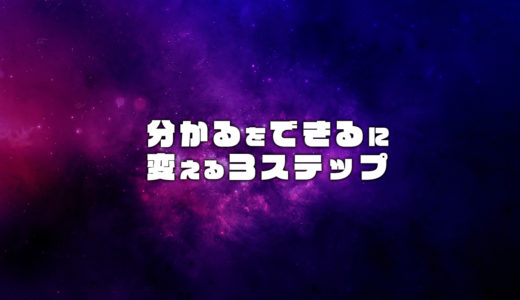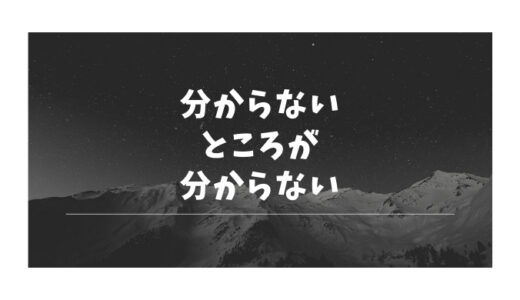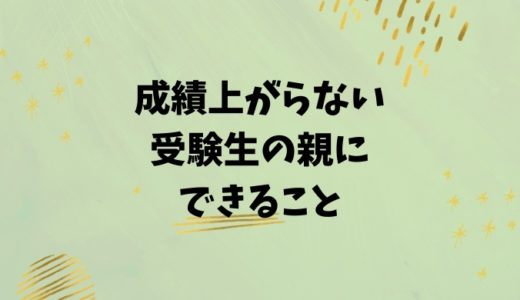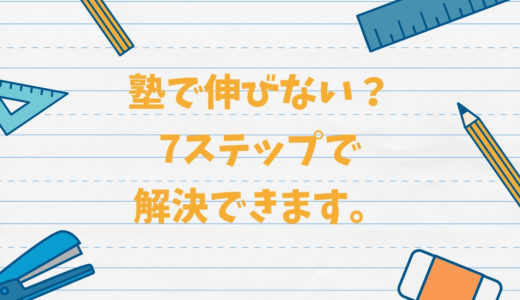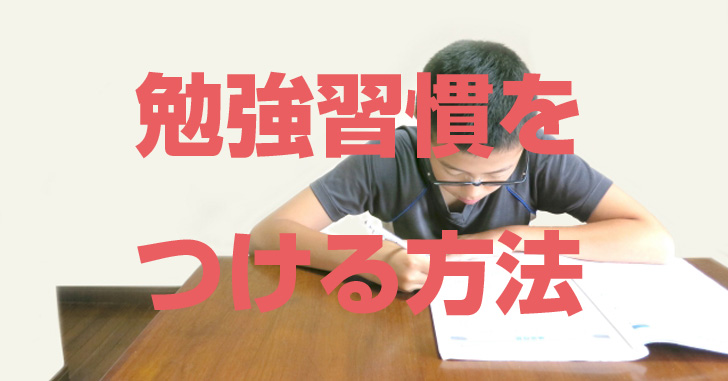こんにちは、中学生専門・伸び悩み解消学習コーチの久松隆一です。


勉強しても点数が上がらない原因、もう突き止めましたか?
勉強しても結果が出ないと、やる気も下がってしまいますよね。勉強してもムダなんじゃないかと疑いたくなる気持ちも分かります。
でも、安心してください。
成績が上がらない原因さえ分かれば、必ず解決できます。じゃあ、一体何が原因なのか…?
勉強しても成績が上がらない原因はほとんどの場合、勉強の仕方にあります。勉強しても伸びないなら、やり方が間違っているのです。
お子さんの勉強の仕方、大丈夫ですか?
伸びないやり方になっていないかチェックしてみてください。
というわけで、今回は勉強しても成績が上がらない原因と、伸び悩みを解消する勉強の仕方について解説します。
原因ごとに正しい対処法を身につけて、爆伸びしましょう。
勉強しているのに点数が取れない3つの要因
ダルビッシュ有投手はこんなことを言っています。
練習は嘘をつかないって言葉があるけど、
頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。
勉強を頑張っているのに成績が上がらないのは、勉強の仕方に問題があるケースがほとんどです。
大阪→東京へ向かうのに、博多行きの新幹線に乗ってしまったとしたら???
当たり前ですが、目指している方向がズレていたら、いくら全力を尽くしても目的地には近づきません。
中学生がよくやってしまうのは、やみくもな努力・・・。それじゃ点数も取れないよね…ってやり方で頑張ってしまっています。
でも、彼らを責めることはできません。だって、どうやって勉強したら良いかなんて、習ってないんですから。
中学校に上がった途端「はい、自分で頑張ってね。」と荒野に放り出されたようなもの。そんな中でも、自分なりの勉強の仕方を、自分一人で獲得できたら理想です。そんな人はラッキー。
でも、ほとんどの方はそうじゃない。最初は少しサポートが必要ではないでしょうか?
まずはお子さんが、中学生によくある勉強しても点数が取れない3つの要因に当てはまっていないか、チェックしてみてください。
- 「覚えたつもり」「分かったつもり」になっている
- 「できる」つもりになっている
- 成長しているけどまだ足りない知識がある
思い当たるふしはありますか?
それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。その原因を解決するための勉強法も併せて紹介します。
勉強しても点数が取れない要因①:「覚えたつもり」「分かったつもり」になっている
勉強の基本は「できない」を「できる」に変えることです。
もう一度言います。
勉強の基本は、
できない→できる
に変えること。
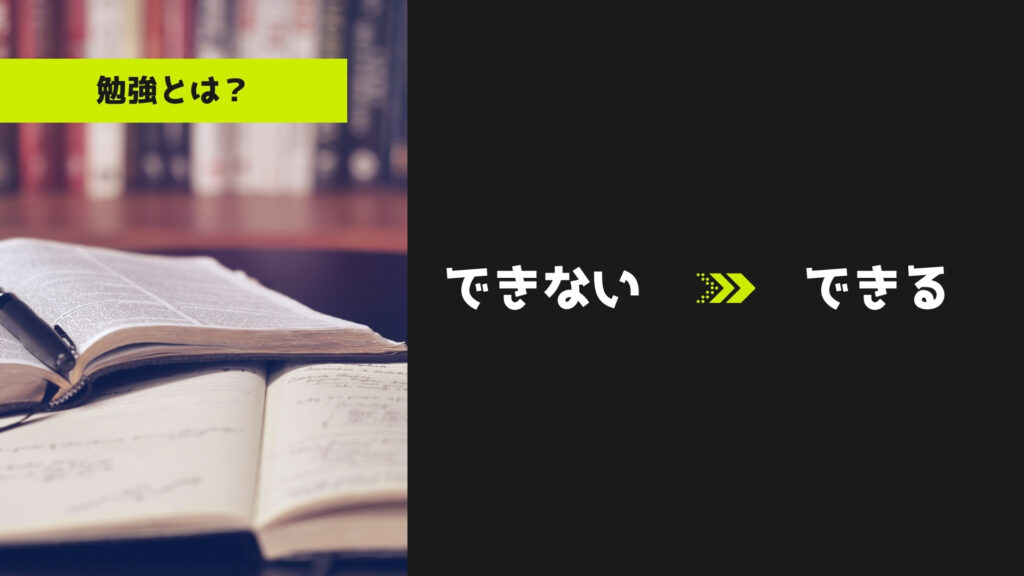
この過程では、
できない→覚えている・分かる→できる
というステップを踏むことになります。
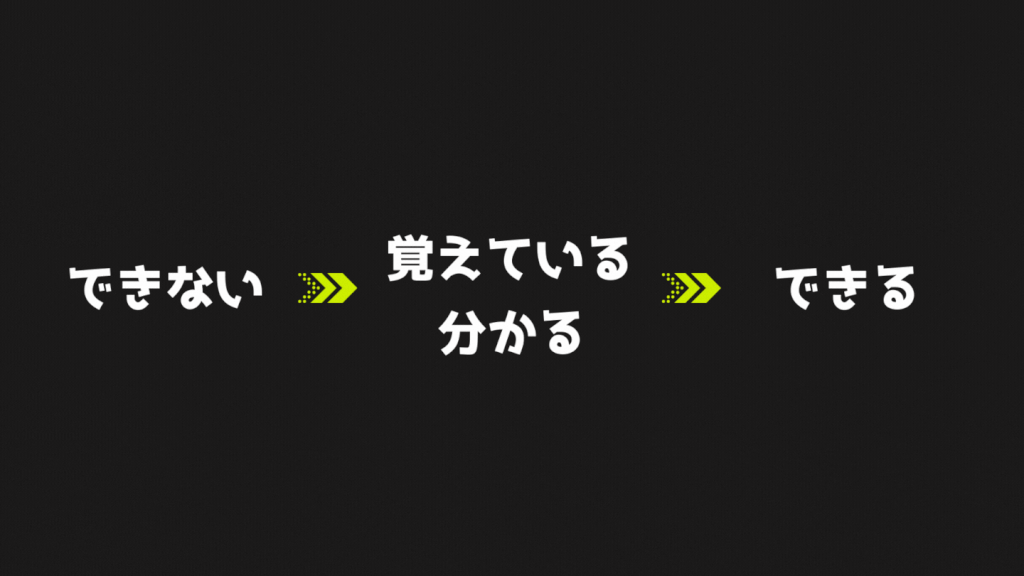
 久松
久松
つまり、まずはじめに、
できない→覚えている・分かる
までもっていかなければなりません。これは暗記or理解するというステップになります。
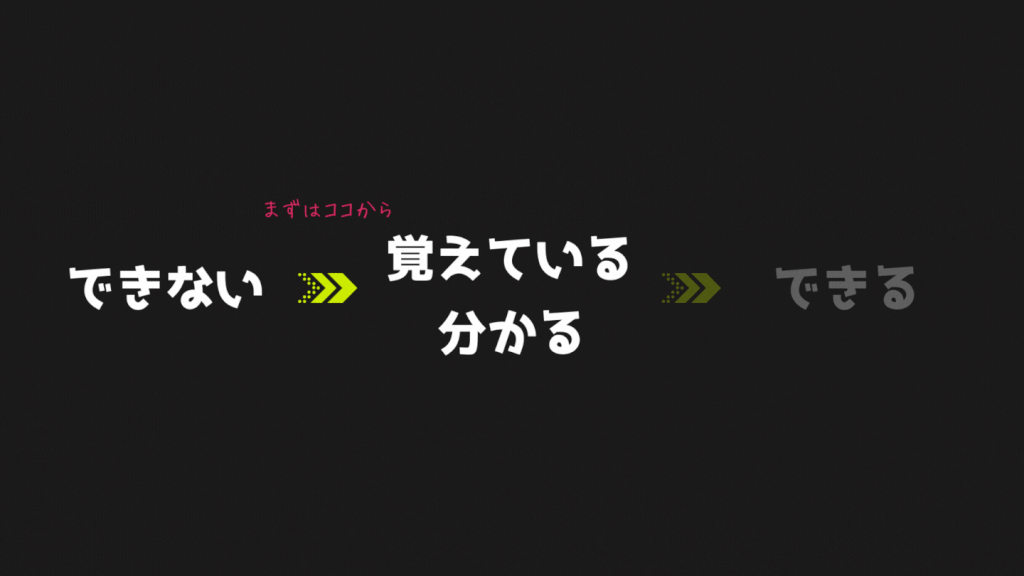
暗記や理解をおろそかにすると、最終的に「できる」ようになりません。当たり前ですよね?
でも、勉強しても成績が上がらない人は、暗記したり、理解したりするステップをクリアできていないことがあります。このことに自分では気づいていません。
つまり、覚えたつもり、分かったつもりになっているのです。
点数が取れない要因は「暗記×」と「理解×」の2タイプ
中学校のテスト問題は「暗記すれば解ける問題」と「理解すれば解ける問題」の2つのタイプに分かれます。
裏を返せば、点数が取れない原因は2つだけ。
- 暗記ができていない
- 理解ができていない
のいずれかになります。
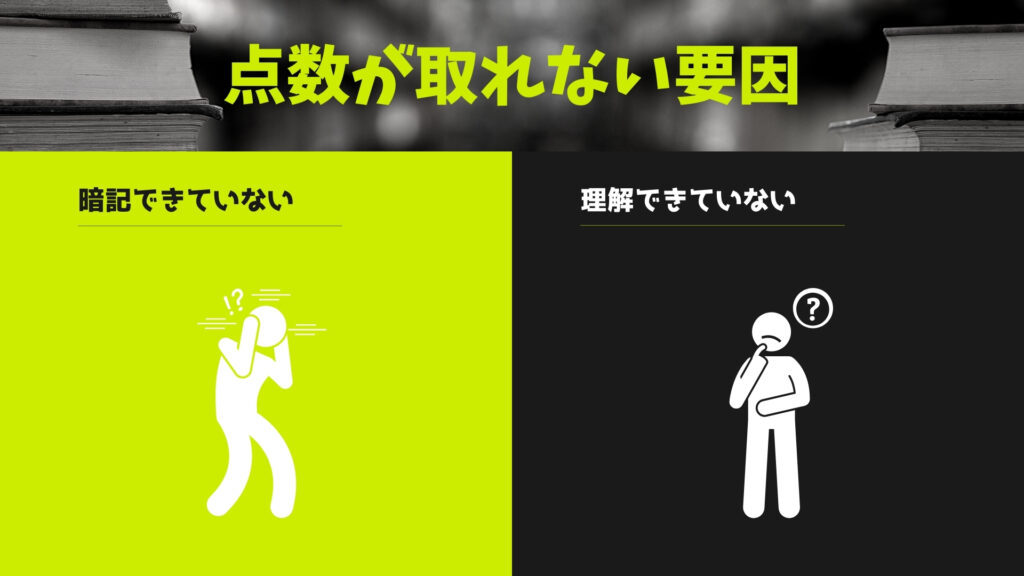
まずは暗記と理解をしっかりして、
できない→覚えている・分かる
にまで持っていきましょう。
このステップでつまずいていると、
 中学生
中学生
 中学生
中学生
なんてことが起こります。
自分の手応えほど点数が取れないのは、「覚えたつもり」「分かったつもり」になっているから。
これを解消するためには、以下で紹介する方法を試してみてください。
「覚えたつもり」を解消するための方法
覚えたつもりになっている方は、かなりの割合で「見て覚える」勉強をしています。
暗記というと、どうしても「覚える」というイメージがあるかも知れませんが、そのイメージは捨てましょう。
あらゆる研究において、「思い出す」練習をしたときに、記憶が強くなることが分かっています。
思い出す練習をする手っ取り早い方法は、自分で「テスト」をすること。
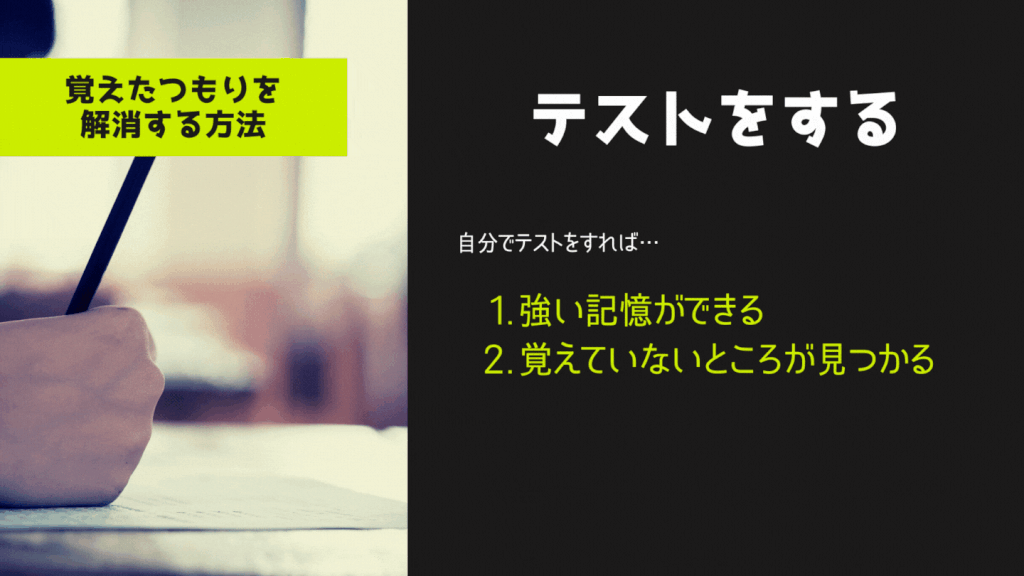
例えば、単語帳を見て覚えている人がいますが、これは「思い出す」練習をしていないのであまり記憶に残りません。でも、なんとなく「覚えたつもり」になってしまう。ここが落とし穴。
かわりに自分でテストをしましょう。単語帳であれば、赤シートがついていたりしますよね?その赤シートを使って何度もテストを繰り返してください。
テストをすれば、自然に自分の知っている知識を思い出す練習になります。これを何度も繰り返すことで、強い記憶ができあがるんです。
しかも、テストをすると「自分が覚えたつもり」になっているところまで発見できます。一石二鳥!
暗記のコツは他にもまだありますが、基本的には「テストを繰り返す」という勉強の仕方に変えるだけでも圧倒的に効果が出ます。ぜひ試してみてください。
「分かったつもり」を解決するための方法
分かったつもりになっているかどうかをチェックして、それを解決する方法は簡単です。
「解き方を自分の言葉で説明すること」
説明できれば、それは理解しているということです。
例えば、こんな間違いをしたとします。
問題:「わたしは昨日英語の勉強をしました」を英訳しなさい。
× I study English yesterday.
この場合、自分の言葉で解き方を説明するとしたら、どうなるでしょうか?
例えば、

のような説明ができればOKですね。それは理解していると言えます。
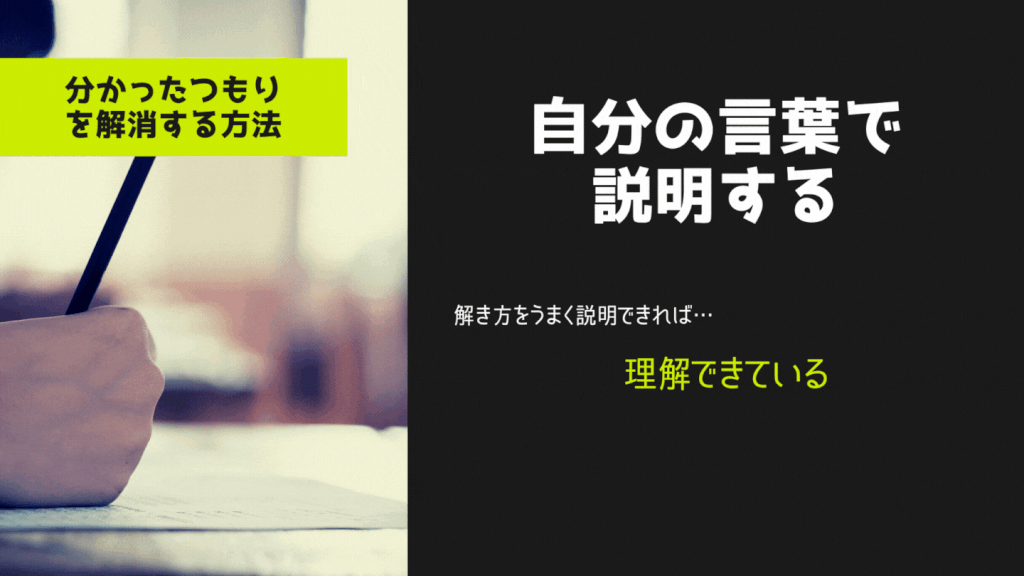
でも、うまく説明できなかったとすれば、それは理解できていないということになります。つまり「分かったつもり」になっています。
この場合、解説をもう一度読み直したり、分かってる人に聞いたりして、改めて理解しなおしましょう。
その上でもう一度自分の言葉で説明する。説明できたらOK。「分かったつもり」は解消されています。
分かったつもりを解消する方法はこちらにより詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
勉強しても点数が取れない要因②:「できるつもり」になっている
お子さんの様子を見て、心当たりはありませんか?


これは、「できるつもり」になっていることが原因で点数を落としています。
つまり、
覚えている・分かる→できる
のステップでつまずいているということ。
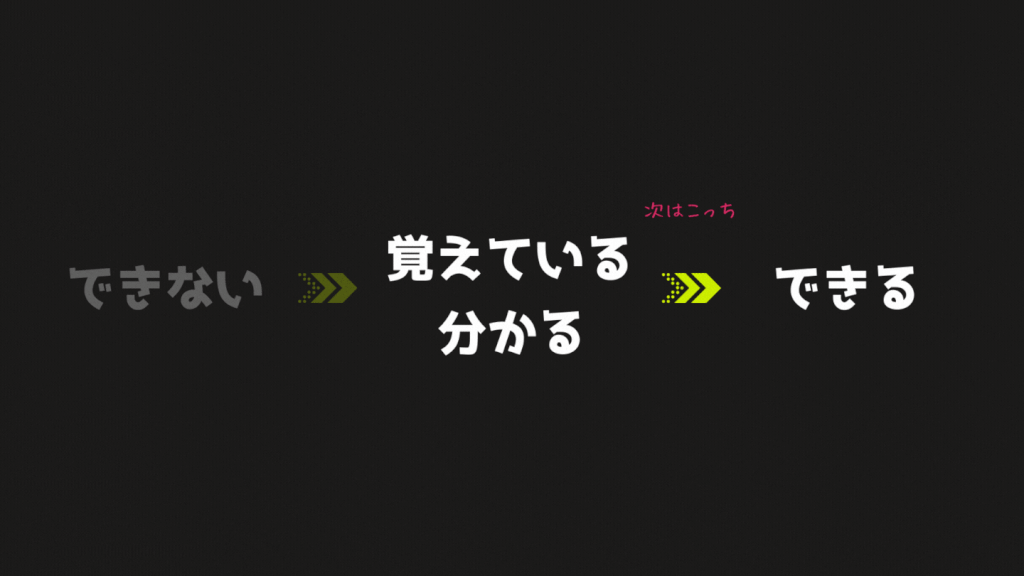
「覚えている・分かる」と「できる」は違う
塾に通っていても点数が取れない子は、このステップが点数が取れない要因になっているケースが圧倒的に多いです。

せっかく塾で習ったことが定着してないんですね。
「覚えている・分かる」と「できる」の違いはココにあります。「できる」とは、テスト本番で、自分ひとりでも正解できる状態です。「できる」状態まで自分をもっていけていないので、自分で思っているほどテストで点数が取れないのです。
「できる」にするためにはどうやって勉強すればいいの?
テスト本番でも、自分ひとりで正解できるようになるために、どうすればいいのでしょうか?
シンプルに言えば、「知識を使いこなせる」ようにしておく必要があります。つまり、反射的に知識が使えるという状態を作り出す必要があるんです。
例えば、使ったことのない新しいスマホを買ったとします。最初から使いこなせますか?きっと無理ですよね。操作の仕方を説明してもらっても、スムーズに使いこなせない。

なんてことも起こります。

でも、使っていくうちに、自然にスマホを使いこなせるようになってきます。勉強もこれと同じ。
つまり、
覚えている・分かる→できる
のステップをクリアするためには、繰り返し解く必要がある、ってこと。
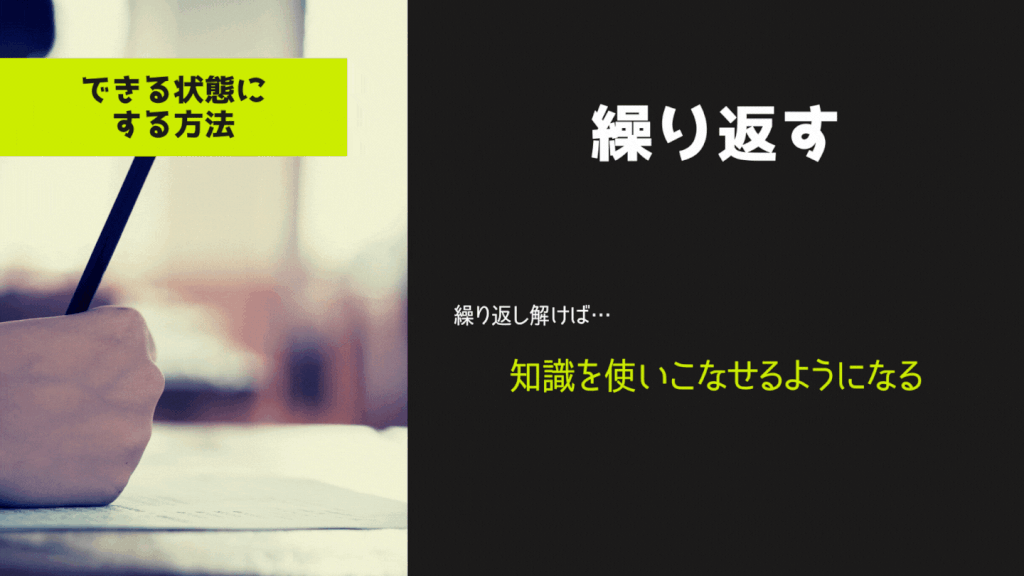
スムーズに使いこなせるようになるまで反復しなければなりません。「覚えた!分かった!」の段階で安心するのはまだ早いのです。
よく中学生がやってしまいがちなのが、
- 授業で「分かった」から、もう自分は「できる」と思い込む
- 人に教えてもらいながら「問題集」を解いて、正解できたからOK!
- 一度正解できたから「もう覚えた!」と油断して、繰り返し復習しない
というパターン。
甘い!
その程度で自分にOKを出してはいけません。大事なのは、テスト本番でも自分ひとりで正解できるか?という視点。
日々の勉強では、何度も反復することを大切にしましょう。その過程では、知識をスムーズに使いこなせているかどうか?を自分でチェックしながら勉強を進めていきましょう。

という基準で日々の勉強を進めてみてください。
日々この基準を守って復習を進めれば、反射的に知識が使いこなせるようになってきます。この基準をクリアして、初めて自分にOKを出しても構いません。
勉強しても点数が取れない要因③:まだ足りない知識がある
これは一番もどかしいケースですね。正しい勉強の仕方で勉強していたとしても、このケースに陥ることがあります。着実に成長はしているけど、点数に結びつかないケースです。
これを知らないと、やる気が続かなくなるのでよく理解しておいてください。
成長しても点数に結び付かないケースは、数学などの理解タイプの問題でしばしば起こります。
基本的に、理解タイプの問題は、いくつかの知識を組み合わせて解くようになっています。例えば、一次関数の式(y=ax+b)を求めなさいという問題があったとしたら、
- y=ax+bの公式を覚えているか?
- 方程式が解けるか?
- 正負の計算ができるか?
といったように、3つの知識が必要です。この3つの知識が揃わないとどうなるか?
得点できません。
大事なので、もう一度。この例の問題ならば、3つの知識がすべて揃っていないと得点できないのです。
ラーメンを作るときには、
- 麺
- スープ
- 具材(煮卵、メンマ、ネギなど)
の3つが必要ですよね?

このうち1つでも揃っていなかったら、ラーメンとしてお客さんに出せません。
これと同じです。一次関数の式を求めなさいという問題なら、
- y=ax+bの公式を覚えている
- 方程式が解ける
- 正負の計算ができる
この3つ、すべてが揃っていないと解けないのです。
たった1つでも足りていない知識があれば、アウト。ビンゴも同じですよね?5つ揃わないとダメ、4つじゃダメです。
いくら日々頑張って成長していても、問題を解くための必要な知識がすべて揃わないと得点できないのです。
本当にこのケースはもどかしい。でも、テストの性質上こうなるのは仕方がありません。大事なのはここで諦めて投げ出さないこと。せっかくあと1つでビンゴなのに、諦めてビンゴカードを捨てないようにしてください。
正しいやり方で勉強しつづけていれば、あなたは日々成長しています。本当にすべきことは、諦めることではありません。足りない知識を発見して、埋めることです。
足りない知識を発見する2つの方法
足りない知識を発見する方法は大きく2つあります。
その1:先生や分かっている人に聞く
一つ目は、塾の先生など完成形が見えている人に聞くこと。
完成形が見えているというのがポイント。完成した姿が見えていない人には、どこが足りていないのか判断できないからです。
例えば、ラーメンを知らない人がいたとしましょう。その人がスープが入っていないラーメンを見たとしても、「これがラーメンなんだな」って思うはずです。
完成形のラーメンを知らない人は、何が足りていないかを判断できないのです。
であれば、ラーメンを知っている人に「このラーメンに何が足りませんか?」って聞くのが一番早いですよね。
勉強なら「この問題を解くために、私は何の知識が足りていないですか?」と聞けばいいのです。できれば、先生の目の前で解いてみてください。
完成形が見えている先生なら、解いている様子を見れば「あ、この子はこの知識が足りていないな」と、すぐに分かります。
そのとき先生から貰ったアドバイスを参考に、自分の足りていない知識を埋めていきましょう。
その2:自分で解き方を説明する
分かっている人に聞くのが一番早いですが、いつも教えてくれる人がいるわけではありません。
そこで、自分で不足している知識をチェックする方法も紹介します。自分でチェックしたい場合は、上でも紹介した「解き方を自分で説明する」を使ってみてください。
スラスラと説明できないところがあれば、そこが不足している知識です。
不足している知識が分かったら、解説を読んだり、インターネットで調べたりして、足りない知識を埋めていきましょう。
余談ですが、勉強の仕方が上手な人は、自分の不足している知識を見つけるのが得意です。自分はどこができないか、を探す習慣があります。
一方、勉強の仕方がヘタな人は、自分の不足している知識を見つけるのが苦手…。
分からないところが分からない状態のまま、右往左往しています。まずは「どこが分からないか、分かる」ようにするのが第一歩です。
番外編:受験生なのに成績が上がらないときは?
お子さんは受験生ですか?
受験生で、それなりに勉強しているのに成績が上がらないのであれば、勉強の仕方以外にも原因があるかもしれません。主に次の3つです。
- 範囲が広いから
- 模試や実力テストは応用レベルだから
- 受験生は忙しいから
これらの原因ならば対策があります。もし受験生なのに成績が上がらない…という方は、こちらの記事にもう少し詳しく原因と対策をまとめてありますので、併せてお読みください。
番外編:塾に行っても成績が上がらないときは?
もし塾に通っているのに成績が上がらないなら、次のパターンに当てはまっていないか、チェックしてみてください。
- 基礎学力が足りない
- 勉強の仕方が悪い
- 勉強量が足りない
この記事では「②勉強の仕方」について深掘りしていますが、他にも「①基礎学力」や「③勉強量」に伸びない原因があるケースもあります。
塾に通っても伸びないと、自信もやる気も失ってしまうので、早めに対策してあげてください。詳しい対策はこちらの記事にまとめてあります。
まとめ
長くなってしまったので、最後に簡単にまとめておきます。
勉強しても点数が上がらない要因は、
- 「覚えたつもり」「分かったつもり」になっている
- 「できるつもり」になっている
- まだ足りない知識がある
という3つでした。
これらの解決策は、
となります。
勉強していても点数が上がらないと自信もなくなってしまうし、それだけは避けたいですね。
もしお子さんが頑張っているのに伸び悩んでいるとしたら、まずは勉強の仕方を見直してみてください。勉強した分だけ自分の成長を実感できたら、自然に自信もやる気も生まれてくるものです。
正しい方法で努力すれば、必ず伸びます。
この記事が少しでも参考になれば幸いです!